水生生物による水質調査
広報ID1010332 更新日 令和7年6月10日 印刷
水生生物による水質調査とは、川にすむ肉眼で見ることのできる大きさのさまざまな生物(指標生物)の生息状況を調べ、その結果から河川の水質状況を知ろうとするものです。
環境保全への意識を高めることを目的として全国的に行われており、盛岡市からも毎年多くの市民が参加しています。
令和6年度水生生物による水質調査結果
令和6年度は、19団体延べ675人が参加し、乙部川、雫石川、大沢川、中津川、北上川、虫壁川、猪去川、米内川、簗川、矢櫃川の10河川20地点で調査しました。その結果、19地点において水質階級1「きれいな水」、1地点において水質階級2「ややきれいな水」と判定されました。
きれいな水(水質階級1)の指標生物
ヤマトビゲラ類
体は太くイモムシ状で、足は3対。色は茶色で、頭と胸は固くて茶色。亀の甲のような砂つぶの巣をかついでいるのですぐ分かる。巣の下面には頭と尾部を出す穴がある。

サワガニ
甲羅の大きさは2~4センチで、色は赤味がかったものから青味がかったものまでおり、比較的浅いところの石の下にいる。腹帯の太いのがメス、長いのがオス。本州で淡水域で一生を過ごすカニはこの種類だけである。

まちがえやすい生物
海に近い川では、海からモクズガニが上がってくるが、モクズガニは、ハサミや足の背に毛が生えている。
ナガレトビゲラ類
体は細長いイモムシ状で、足は3対。腹の色はうすく、やや緑がかっている。頭と前の胸が固くなっているが他はやわらかい。肉食の種類が多く、上流の水温の低い、きれいなところにいる。幼虫は網や巣をつくらずに石の上や間を歩く。

ヘビトンボ
大きな強いアゴをもち、腹に糸のような横にのびる長い突起があり、付け根にエラがある。肉食性で他の水生昆虫をエサにする。川底の石の下にいる。

ブユ類
体はこげ茶色で、腹の後方が太くなっている。お尻に吸盤とエラがあり、吸盤で流れの速いところの石の表面や草についている。日本でおよそ30種。人の血を吸うのはアオキツメトゲブユを含めて5種類くらいである。
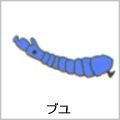
カワゲラ類
尾は2本で、胸の下面や腹の末端にふさ状のエラがある。足のツメは2本。渓流の石の間や、流れがゆるやかで落葉などがたまっているところを好んですんでいる。日本産は約150種類。
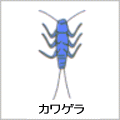
まちがえやすい生物
カゲロウ類とまちがえやすいが、腹に木の葉状のエラがない。
ヒラタカゲロウ類
足のツメは1本で、尾は長く2本。目が上についており、体全体が平たくカレイのような形。腹の両側に木の葉状の大きなエラがある。流れの速いところの石に体を密着させて生活している。
まちがえやすい生物
カワゲラとまちがえやすい。
アミカ類
頭から2本の触角を突き出し、ロボットのような形をしている。腹に6個の吸盤があり、吸盤で急流の岩の上についている。

ナミウズムシ
体の色は茶色、ねずみ色、黒色。体はやわらかく、切れやすい。また、体には節(体節)がない。一般にプラナリアとよばれ、小川の浅い流れの石の上を流れるようにはう。
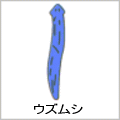
まちがえやすい生物
ヒル類に似ているが、ヒル類には腹の前後の端に吸盤があり、シャクトリムシのように動く。
ややきれいな水(水質階級2)の指標生物
カワニナ類
殻は細く、長い。殻の上部が欠けていることが多い(殻高1.5~3センチ)。殻の表面は黄土色またはこげ茶色で、ザラザラしている。石に付着していることもあるが、砂まじりの川底にいることもある。塩分のあるところにはいない。

ゲンジボタル
体は黒色で、胸の一番前の節(頭のように見える)に、トランプのスペードの模様がある。ヘイケボタルはよく似ているが、ゲンジボタルの方が大きい。ヘイケボタルでは、十文字形の模様がある。
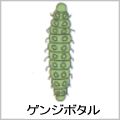
オオシマトビゲラ
頭から胸にかけて固く、うすい茶色である。他は茶色から緑色でやわらかく、頭の上部の平たい部分が広いのが特徴。さなぎは石粒などを使って固めた巣で過ごす。

まちがえやすい生物
シマトビケラとまちがえやすい。
コオニヤンマ
体は赤茶色で、薄い平らな広葉状あるいはうちわ状の形をしている。触角もうちわ形。流れの比較的おだやかなよどみの底で生活している。
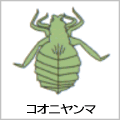
ヤマトシジミ
二枚貝で、殻は小さいうちは青緑色だが、成長すると黒色になる。

まちがえやすい生物
マシジミとまちがえやすいが、マシジミは淡水にすんでいる。
コガタシマトビゲラ類
頭の先に小さなくぼみがあるのが特徴で、頭と胸は赤茶色をしている。腹は鮮やかなうす緑色から緑がかった茶色、あるいは茶色などいろいろな色をしている。

ヒラタドロムシ類
体は固く、平たい円形か卵形で、色は黄色か茶色。足は3対あるが、背の方からは見えない。流れの速い瀬の石の表面について生活している。

イシマキガイ
殻は固く、石についている。主に海水が少し混ざっている汽水域にすんでいる。

きたない水(水質階級3)の指標生物
イソコツブムシ類
陸にいるダンゴムシに似て、体を丸めることができる。砂まじりの川底や石の間にいる。海水の少し混じった汽水域にすんでいる。

ミズカマキリ
大きさは7センチくらいで体は細長い。陸上にいるカマキリのように、前足でほかの小動物をつかまえて、その体液を吸う。池や沼、水田にすんでいるが、川岸の流れのゆるやかな場所にもすんでいる。
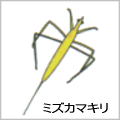
ニホンドロソコエビ
体は縦に平たく、ちぎれやすい。また、細長い触角があり、泥の多い川底にいる。海水の少し混ざった汽水域にすんでいる。
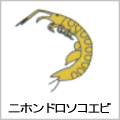
シマイシビル
大きさは3~4センチで、はげしく伸び縮みし、体節がある。体は平たく、背面から見ると円柱形、長卵形で、腹の前後の端に吸盤があるが、前の吸盤は見にくい。水に沈んでいる石などの裏側にすんでいる。淡水域にいる日本産ヒル類は約30種類。
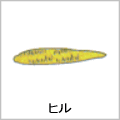
まちがえやすい生物
ウズムシ類とまちがえやすいが、シマ模様がありからだは固い。
タニシ類
タニシの主な種類は4種類である。殻は薄く、赤茶色のふたがあり、泥底にすんでいる。

ミズムシ
体長は大きくなっても1センチくらいで、ダンゴムシに似た形で平たくなっている。足は5対以上で、ゆっくりはう。体は汚れたような灰色または茶色。川にすむのは1種類で、あとは地下水にすむ。
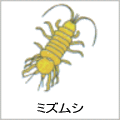
とてもきたない水(水質階級4)の指標生物
アメリカザリガニ
大きさは10センチくらいで、流れがゆるやかで浅い泥の多い川底にすんでいる。北アメリカから入ってきた外来種。
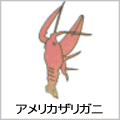
まちがえやすい生物
北海道や東北地方などには、きれいな水にすむもともと日本にいた別種類のザリガニがいる。
チョウバエ類
大きさは8ミリくらいで、細長く、足はない。下水、排水溝などにすんでいる。尾に長い突起(呼吸管)がある。
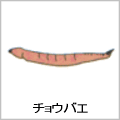
ユスリカ類
中型のユスリカで大きさは1.5センチぐらい。赤色。腹の下の方の節に2対のエラがある。流れのあるところに泥などチューブ状の巣をつくって生活している。
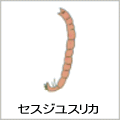
まちがえやすい生物
赤色のユスリカは非常に多くの種類があり、上流のきれいな場所で見つかるものもある。
エラミミズ
大きさは最大4センチくらい。ピンクや赤色の糸状でちぎれやすく、頭ははっきりしない。頭を泥の中に入れ、尾を水中に出してゆすり、水の流れをつくって呼吸している。水中の酸素量が少なくても生活できる。尾に多くの糸状のエラがある。

サカマキガイ
殻のとがった方を上にして見て、口が左側についているのが特徴。流れのないところでは水面に逆さ向きになっていることがある。
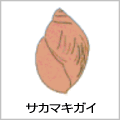
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境企画課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-626-3754 ファクス番号:019-626-4153
環境部 環境企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


