麻しん(はしか)
広報ID1019349 更新日 令和6年11月27日 印刷
| 病原体 | 麻しんウイルス |
|---|---|
| 症状 | 発熱(二峰熱)、全身の発疹、風邪様症状(咳、鼻水、目の充血) |
| 感染経路 | 空気感染、飛沫感染、接触感染 |
| 陽性者から他の人への感染 | する |
| 予防方法 | 予防接種 |
感染症法に基づき「5類感染症:全数把握義務」に定められています。
麻しんの詳細
とても感染力の強い病気です。
麻しん(はしか)は、麻しんウイルスによって起こる感染症です。感染力が非常に強く、空気感染、飛沫感染、接触感染などのいずれの感染経路でも感染し、免疫を持たない人が感染するとほぼ100%発症します。
日本は、2015(平成27)年3月に、世界保健機関西太平洋地域事務局により、麻しんの排除状態にあることが認定されました。しかしその後も、海外で感染し国内で発症した患者を発端として、イベント会場や空港など沢山の人が集まる施設での集団感染が起きています。
原因と感染経路
原因
麻しんウイルス
感染経路
空気感染、飛沫感染、接触感染
感染可能期間
症状が出現する1日前から解熱後3日を経過するまで
潜伏期間と症状
潜伏期間
約10~12日間(最大21日間)
症状
典型的な麻しんの症状とは
- 発熱(二峰熱)
- 全身性発疹(顔面や耳の後ろから出始め、身体全体に拡がる)
- 鼻水、咳、目の充血
などが挙げられます。
風邪症状で始まり、重症化することもあります
麻しんに感染すると、約10~12日間の潜伏期間を経て、発熱や咳、鼻水など、風邪のような症状が数日間持続し、熱が下がるタイミングで口腔内の頬の内側に小さな白色の斑点(コプリック斑)が現れます。その後再び39度以上の高熱と発疹が出現します。感染しても、合併症が無ければ、発症から1週間~10日程度で症状は徐々に収まります。
重症化すると肺炎や中耳炎、稀に脳炎を合併することもあり、麻しんに罹患した1000人のうち1人が死亡すると言われています。ごく稀に感染してから数年後に発症する亜急性硬化性全脳炎になる人もいますが、神経症状が徐々に悪化して発症後数年~数十年を経て死に至ると言われています。
修飾麻しんについて
麻しんに対する免疫はあるが十分ではない人(例えば:幼少期に1回だけ予防接種をしていた等)が麻しんウイルスに感染した場合、軽症で非典型的な症状を呈することがあります。このような麻しんを「修飾麻しん」と呼びます。感染力も普通の麻しんと比較すると弱いですが、周囲への感染力が全く無いわけではありませんので、注意が必要です。
麻しんの症状が見られたら
早急に受診しましょう
麻しん様の症状が現れた場合は、事前に医療機関に電話して受診時間や方法について指示を受け、できるだけ早く受診しましょう。診察の結果麻しんが疑われる場合、検査等により麻しんが否定されるまでは、外出を控えてください。
予防方法
予防手段はワクチンのみ
麻しんは、非常に感染力が強く、手洗いやマスクだけでは十分な予防ができません。このような感染症で、効果を発揮するのが「予防接種(ワクチン)」です。
麻しんの予防接種は、生後1歳から2歳未満と小学校就学前1年間(幼稚園・保育園年長時の4月1日から翌年3月31日まで)の2回接種が無料で受けられます。小学生以上の方は、母子手帳などを見て自分の予防接種歴について確認しましょう。医療従事者や教育関係者、海外渡航予定がある方で、未接種の方や接種歴がわからない方は、麻しんの抗体価検査とワクチン接種を受けることをお勧めします。
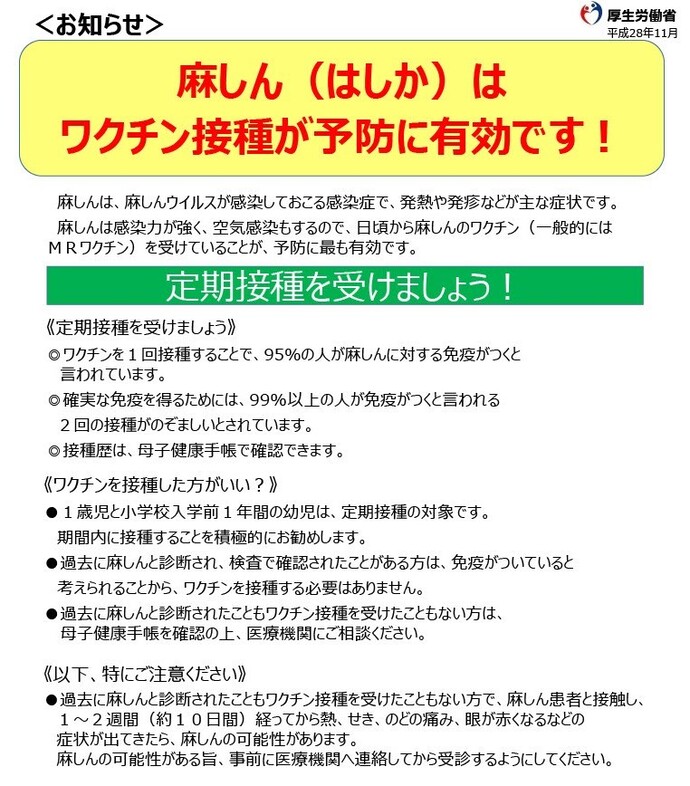
- 麻しん・風しん (厚生労働省)(外部リンク)
- 麻しん(はしか)に関するQ&A (厚生労働省)(外部リンク)
- 麻疹とは (国立感染研究所)(外部リンク)
- 子どもを対象とした予防接種 (盛岡市ホームページ)
治療方法
麻しんに対する特異的な治療法は無く、発熱や咳などの症状を和らげる対症療法となります。細菌性肺炎や中耳炎などを合併した時には抗菌薬を使用することもありますが、抗菌薬は麻しんウイルスには効果がありません。
学校保健安全法における取り扱い
学校保健安全法では、麻しんは第二種感染症に定められており、解熱後3日を経過するまで出席停止とされています。また、流行状況によって学校医の判断により出席停止の指示が出る場合がありますので、学校に確認してください。
医療機関のみなさまへ
確定診断と感染予防に御協力ください
1. 麻しんを診断した医師は、直ちに保健所へ届出をお願いします。
麻しんは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき、医師の診断後直ちに保健所への届出が必要な疾患です。
麻しんは、その特徴から迅速な感染予防対策及び遺伝子検査等が必要となることから、臨床診断の段階で保健所へ連絡のうえ、調査及び検体の採取等に御協力をお願いします。
<連絡先>
盛岡市保健所 指導予防課 感染症対策担当 電話019-603-8244 ファクス019-654-5665
※ 休日及び夜間は、市役所代表(電話019-651-4111)に御連絡ください。
2. 院内感染対策に留意してください。
麻しんは、非常に感染力が強く、診療を担当した医療従事者の感染事例が複数発生しています。院内感染を防ぐため、平時から職員の予防接種歴を確認するとともに、麻しんが疑われる患者が受診した際の対応についての準備をお願いします。
具体的な対応については、国立感染症研究所の「医療機関での麻しん対応ガイドライン」を御参照ください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所 指導予防課 感染症対策担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8244 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


