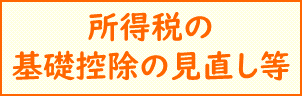いわゆる「年収の壁」に関する令和7年度税制改正の主な内容について
広報ID1052657 更新日 令和7年11月14日 印刷
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、
- 給与所得控除の見直し
- 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ
- 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
※ 改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
※ このページでは令和8年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。
※ 所得税に関する改正内容については下記リンクより国税庁ホームページをご確認ください。
1.給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
|
給与等の収入金額 |
改正前給与所得控除額 |
改正後給与所得控除額 |
|---|---|---|
|
1,625,000円以下 |
55万円 |
65万円 |
|
1,625,000円超1,800,000円以下 |
給与等の収入額×40%-10万円 |
|
|
1,800,000円超1,900,000円以下 |
給与等の収入額×30%+8万円 |
|
|
1,900,000円超3,600,000円以下 |
給与等の収入額×30%+8万円 |
改正なし |
|
3,600,000円超6,600,000円以下 |
給与等の収入額×20%+44万円 |
|
|
6,600,000円超8,500,000円以下 |
給与等の収入額×10%+110万円 |
|
|
8,500,000円超 |
1,950,000円(上限) |
家内労働者等の必要経費の特例について、必要経費の最低保障額の引き上げ
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。
2.同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ
令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 |
改正前 (給与収入のみの場合の収入金額) |
改正後 (給与収入のみの場合の収入金額) |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
|
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
|
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
|
勤労学生の合計所得金額 |
75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
【例】配偶者や扶養親族の令和7年(2025年)中の収入が給与収入のみの場合
給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、同一生計配偶者や扶養親族となるため、扶養している方の令和8年度(2026年度)の市民税・県民税において配偶者控除等の適用を受けることができます。
また、給与収入が106万5千円以下(改正前:96万5千円以下)であれば、被扶養者自身に市民税・県民税は課税されません。
|
令和7年中の給与収入金額 (令和7年中の合計所得金額) |
配偶者控除・扶養親族の対象(注1) |
被扶養者自身の 「市民税・県民税」の課税(注2) |
|---|---|---|
|
106万5千円以下 (41万5千円以下) |
対象 |
非課税 |
|
106万5千円超123万円以下 (41万5千円超58万円以下) |
対象 |
課税 |
|
123万円超 (58万円超) |
対象外 |
課税 |
(注1)配偶者控除は、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用を受けられません。
また、扶養親族が30歳以上70歳未満で国外に居住している場合は、留学生や障がい者、生活費等に充てるための支払を38万円以上している場合に限り、控除の対象とすることができます。
(注2)市民税・県民税が課税されない方は、原則として前年中の合計所得金額が41万5千円以下の方です。扶養親族のいる方や障がいのある方・未成年者である場合などの場合は、非課税となる前年中の合計所得金額が変わります。詳しくは「市民税・県民税の非課税基準」を参照してください。
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
大学生年代の就業調整に対応するため、令和8年度の個人住民税から、19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が95万円(給与収入160万円に相当)までは、納税義務者が扶養控除(特定扶養親族)と同額(45万円)の所得控除を受けられ、大学生年代の子等の合計所得金額が95万円を超えた場合でも納税義務者が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みが新たに設けられます。
対象者
以下のいずれにも該当する人と生計を一にする納税義務者
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
- 控除対象扶養親族に該当しない
控除額
|
控除区分 |
特定親族の合計所得金額 (給与収入のみの場合の給与収入金額) |
個人住民税控除額 |
所得税控除額 |
|---|---|---|---|
|
扶養控除 (特定扶養親族) |
58万円以下 (123万円以下) |
45万円 |
63万円 |
|
特定親族特別控除 |
58万円超85万円以下 (123万円超150万円以下) |
45万円 |
63万円 |
|
85万円超90万円以下 (150万円超155万円以下) |
45万円 |
61万円 |
|
|
90万円超95万円以下 (155万円超160万円以下) |
45万円 |
51万円 |
|
|
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
41万円 |
|
|
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
31万円 |
|
|
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
21万円 |
|
|
110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
11万円 |
|
|
115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
6万円 |
|
|
120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
3万円 |
※収入金額は給与のみの場合の参考です。ほかの収入がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
よくある質問
Q1.給与所得控除とはなんですか?
A1.給与所得者が収入を得るために必要な経費を概算で控除する制度です。給与収入金額に応じて段階的に給与所得控除額が適用されます。
Q2.給与所得控除が引上げられるとどうなりますか?
A2.給与収入金額から給与所得を算出する際の必要経費にあたる金額が増えることになり、給与所得金額が減少します。所得金額が減少することになるため、税負担の軽減につながります。
Q3.すべての人が引上げの対象ですか?
A3.給与収入金額が190万円以下の方のみが引き上げの対象です。190万円を超える区分の方に改正はありません。
Q4.令和7年の収入が給与収入のみの場合、令和8年度分の住民税は非課税になるのはいくらまでですか?
A4.住民税が非課税になるのは、給与収入が106万5千円までです。下記の表を参考にしてください。
Q5.令和7年の収入が給与収入のみの場合、扶養に入ることができるのはいくらまでですか?
A5.扶養に入ることができるのは、給与収入123万円までです。下記の表を参考にしてください。
| 給与収入 | 課税要件の変更など |
|---|---|
| 106万5千円超 | 市県民税均等割(6,000円、森林環境税を含む)が課税になります。 |
| 110万円超 |
市県民税所得割(所得等に応じて課税される税金)が課税になります。 (注)所得控除の額によっては課税されない場合があります。 |
| 123万円超 | 扶養親族に入れなくなります。 |
【扶養人数や本人の状況(ひとり親、障害者等)によって要件が異なります。】
Q6.具体的にいつからいつまでの所得が扶養控除判定の基礎となるのですか
A6.前年1月1日から12月31日の所得が個人住民税における扶養控除の判定の基礎となります。
令和8年度課税の個人住民税の場合、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの所得が対象です。
Q7.特定親族特別控除に該当する場合も扶養親族として扱われますか
A7.特定親族特別控除に該当する場合は、合計所得金額に応じて控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第二・第三係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8497 019-613-8498 ファクス番号:019-622-6211
財政部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。